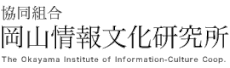津山市/作州絣
【vol.1】 さくしゅうがすり
城下町津山で庶民に愛された木綿絣は、今も地元の人の力で継承される工芸に。

▲日名川さん着用の作州絣の着物と帯は自作。お出かけ着になるものは鶴や桐など縁起のよい柄が織られた生地を使うことが多い。
「作州絣」は、城下町である津山を中心に伝承されてきた木綿絣の織物。
太めの木綿糸に、柄を出したい部分が白くなるよう紐状のものをくくり付けて藍で染めた後に織られ、経糸と緯糸の合わせ方で柄の表情が変化していく。糸がずれないよう繊細な作業が必要で、より鮮明に柄を浮かび上がらせるのが熟練度が高いとされている。
柄は、水玉のような「豆腐柄」と呼ばれるものや雪の結晶などシンプルなもの、さらには津山藩主を務めた森家ゆかりの鶴や松平家の家紋である三つ葉葵などの柄もあったというのが津山らしい。
江戸時代に出雲の地から綿栽培と綿織物の技術が持ち込まれたことがルーツ。それらで織った素朴で丈夫な生地は、もとは庶民が自分たち用に家庭で手織りし日常着として普及していった。まず着物や作業着に仕立て、生地が少し傷んでくると子どものおしめや雑巾に、最終的にはかまどの火付けにと、何度も再利用して無駄にせず生活に寄り添う織物として津山の人に親しまれていたものだった。

▲「作州絣保存会」の会員が制作した、作州絣の反物。
戦後に津山市の産業復興のひとつとして官民で絣織物の研究・生産が進み産業化され、昭和30年代に最盛期を迎えるが、久留米絣や備後絣などのほかの絣に押され、生産量が減っていく。
最後の一軒になったのが、広島県府中市で織元の息子として生まれた杉原博さんが率いる『大一織物』だ。織物の製造現場のそばで育ち、自然と技術が身に付いていた杉原博さんによる作州絣は柄の美しさや技法など評価が高く、昭和56年には手織作州絣が岡山県郷土伝統的工芸品に指定されるまでになった。しかし杉原さんが他界すると、作州絣を織れる人はいなくなってしまった。

消えかけていた作州絣の伝統を受け継ぐことになったのが、杉原家と縁があり洗張・染物業を営んでいた家に嫁いだ、現「作州絣保存会」会長の日名川茂美さん。
まず、『大一織物』に残っていた反物を託され販売することに。しかしこれらの反物がなくなったら作州絣がなくなってしまう。「この文化を継承していかないと」との危機感を持ち、自らも織る技術を身に付けようと鳥取短期大学絣研究室に入学。その後、作州絣最後の織元の杉原さんの親族にも腕を認められ、平成24年に「作州絣保存会」を発足させるまでとなった。
同じ年に、後継者育成のために、織るだけでなく糸を紡ぐところから一年を通じて学ぶ「作州絣織り人養成講座」も開講。今では20代から70代までの織り人が約30人も育ってきている。そのほか、津山市内の小学校でのワークショップや一般の人への体験講座など普及活動にも努めている。
「津山の故郷の心である作州絣。地域の人に使ってもらえるようになりたいし、後々には津山の街の通りを歩いていると機織りの音が聞こえるようになるのが私の願いです」と、日名川さんは穏やかにほほ笑んだ。
▲(左)柄のベースになる模様下地。この上に糸を添わせ、染めない部分に紐をくくり付け染色を施す重要な工程だ。
(中)これは両方の糸を染め、柄を出すタイプの絣。経糸では縦模様に、緯糸では横模様に染め、両方が合わさることで井桁柄が完成する。
(左)御朱印帳やお手玉、ストールなど、反物以外の商品も作られ、『作州民芸館』や『ザ・シロヤマテラス津山別邸』『津山鶴山ホテル』などで販売。

「作州絣」をこちらで体験
「卓上手織機を使うコースター作り体験」
極太染め糸を使いコースターを1枚織る(約1時間)。
絣を織る愉しさを感じたいなら、藍染めの極太糸を使った柄合わせの難易度が上がる体験がおすすめ(写真左)。
より本格的に作州絣の製造工程を知りたい人向けに、綿の状態からほぐして糸に紡ぐ工程や作州絣の本物の織機で織る体験ができるコースも用意されている。
会場:作州絣工芸館(津山市西今町3)
電話:0868-23-0811
休:不定 ※電話にて要問い合わせ
料金:①極太染糸縞柄コースター 1名 4,000円
②藍染絣柄コースター 1名 5,000円(いずれも2名~、1名の場合はいずれも1名6,000円、5日前までに要申込み)
③絣が織れるまでの工程のレクチャー、綿繰り、糸紡ぎ、高機で織り体験 1名 2万円(2カ月前までに要申込み)
駐車場:あり
※『オセラ2024年10月25日号』にて掲載。
※掲載の情報は、掲載開始(取材・原稿作成)時点のものです。状況の変化、情報の変更などの場合がございますので、利用前には必ずご確認ください。