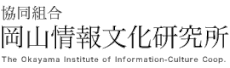新見市/神代和紙
【vol.3】こうじろわし
守りたい、後世に伝えたい気持ちで、消えかけていた神代和紙を復活。

▲新見市の『紙の館』では厚みのあるものや繊維が長いもの、塵入り(ちりいり)のものなど特徴の異なる和紙を流し漉(す)きで制作。さらに着色した和紙も販売する。
神代和紙という伝統文化が残る新見市神郷下神代地区は、山に囲まれた地域。冬の厳しい寒さと、清らかな水が豊富な点が紙漉き(かみすき)に適しており、「強く軽い」神代和紙は質の高さが評判だ。
室町時代には、『東寺』(京都府)との縁があり、神代で漉(す)かれた和紙が『東寺』へも献上され、さらに早く送ってほしいという催促まで届いたという記録も残っている。それほど信頼された和紙だったのだろう。
また、下神代は和紙の原料となる植物の楮(こうぞ)と三椏(みつまた)の両方が育つ貴重な土地でもあった。農閑期の冬の仕事として、楮や三椏を育てる人がいるいっぽう、紙を漉く人がおり、分業で神代和紙の生産が行なわれていた。

▲現在の、楮9割、三椏1割の割合で混ぜて和紙を漉くスタイルは、高尾和紙仕込み。「流し漉き」では簀桁(すけた)を左右前後に揺り動かして繊維を行き渡らせいく。
しかし、明治時代に安価な洋紙の需要が高まり、製紙作業の機械化も進むと、手漉き和紙作りは衰退の一途をたどる。手漉き和紙の材料であり紙幣にも使われる三椏は、近年まで下神代で育てていたがなくなり、神代和紙の文化は途絶えていった。
その復活の動きが出たのは1990年。神代和紙の文化を伝えるため、新たに新見市神郷下神代地区に造った『夢すき公園』の中に『紙の館』が行政主導で整備されたのだ。ただ、紙を漉ける人が下神代にいなかったため、同じ新見市で高尾和紙を漉いていた赤木さんに教えを乞うたという。
次の大きな動きは、当初から復活に携わっていた忠田町子さんに加え、地元出身の土屋俊介さん、祖父母が下神代にいるという京都出身の仲田紗らささんという若手の担い手が現れたこと。そこで2016年に「神代和紙保存会」を結成し、『紙の館』を拠点に神代和紙の復活のため活動することになった。

▲左から、保存会の主なメンバーである仲田さん(左)、忠田さん(中)、土屋さん(右)。
若手2人がさまざまな試みを企画するが、「ベテランの忠田さんがフットワーク軽く協力してくれるので心強い」と仲田さん。
津山市の横野和紙や備中和紙、島根県・石州和紙、岐阜県・美濃和紙など全国の和紙の産地に積極的に学びに行った。視察に行くなかで、素材が生きるような楮や三椏を煮る方法や漉き方を学んだが、紙漉き職人の、「紙は心で漉くものだ」「今まで漉いた紙で納得できた紙はない」という、ふとした発言も印象に残ったという。
その後、自分たちで目の前の紙漉き作業に向き合うなかで、同じように紙を漉く難しさを知ることになるが、だからこそ探求しがいがあると感じている。
▲(左)2018年からは、土屋さんが和紙の原料である楮を自ら育てるように。 (中)和紙作りは原料の楮や三椏を鍋で4時間蒸して表の黒皮、その内側の白皮を一緒にはがす下準備から始まる。 (右)白皮を煮て黒皮やごみなどを取り、ようやく紙漉きができる。写真の楮は繊維が長く、絡みやすいので強い紙ができる。
また、地元の人でも認知度が低いという神代和紙を知ってもらうための活動にも力を入れている。そのひとつが地元小学校の卒業証書の用紙制作。小学6年生自ら紙漉きをしてもらう一生思い出に残る取り組みだ。
さらには神代和紙を使ったものづくり体験や、毎年8月には『夢すき公園』に神代和紙で作った燈籠や風鈴を飾るイベントも実施。将来的には、11月から3月の厳冬期に行なわれる、紙漉きの原料の楮や三椏の皮むき体験も参加を募りたいという。
「千年後に残ることもある和紙。この文化を絶やさないためにいろんな人に見て体験してもらえるよう活動していきたい」と仲田さんは語った。

▲神代和紙を、はがきやご祝儀袋やポチ袋にして販売。コーヒーフィルターは土屋さん作。
『神代和紙』をこちらで体験
「オリジナル風鈴づくり/一閑張(いっかんばり)ワークショップ」
6色の神代和紙を、ガラスの風鈴に切ったり手でちぎったりして好きなように水で貼り付ける風鈴づくり。和紙の短冊には絵も描ける。
一閑張は、竹籠にちぎった和紙を柿渋で貼り付け、最後に好きな紙で飾り付けできる。
いずれも開催日程は未定で、『紙の館』のほか、県内各地でワークショップを行なう予定。毎年8月に『夢すき公園』で開催する「かみさま夢風鈴」期間中にもワークショップを開催する。
また、11月~3月の間で楮と三椏の皮むき体験も開催する予定。詳細はホームページで確認を。
会場:紙の館(新見市神郷下神代1977-1 『夢すき公園』内)ほか
料金:各1500円 ※2週間前までに要申込。開催日時についてはHPを要確認。皮むき体験は参加無料、当日参加可能、軍手持参のこと
電話番号:090-9985-5271(神代和紙保存会(仲田))
※『オセラ2025年2月25日号』にて掲載。
※掲載の情報は、掲載開始(取材・原稿作成)時点のものです。状況の変化、情報の変更などの場合がございますので、利用前には必ずご確認ください。