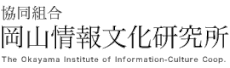倉敷市/玉島のお茶文化
【vol.2】たましまのおちゃぶんか
江戸時代から続く玉島のお茶の文化に触れ、風流を愛する心の豊かさと奥深さを知る。

▲画像は季節の意匠が美しい『松涛園』の和菓子。『松涛園』倉敷市玉島中央1-12-18 電話:086-526-7655

▲『器楽堂老舗』の茶室「五雲亭」にて表千家流のお茶を体験。講師は器楽堂ゆう子さん。
岡山県西部を流れる、県下三大河川のひとつ、高梁川。その河口そばにある玉島は、江戸時代に港が開かれ、中国地方屈指の商業港として栄えた。当時この地域では京風のお茶が流行し、最盛期は約400の茶室があったとされる。今でもいくつかの茶室が旧港周辺に集中して残り、「茶室群」として全国的にも珍しい地域資源となっている。
玉島のお茶文化は港の発展に関係する。もともとこの一帯は島々が浮かぶ遠浅の海だったが、1600年代に備中松山藩主・水谷勝隆・勝宗が干拓を進め、水路や水門、港を普請した。成功の鍵となったのは、羽黒神社のある羽黒山(旧阿弥陀島)と円通寺の柏島の海を潮止めした長さ約400メートル、幅約50メートルの「新町堤防」である。この堤防により、海側の水深が約九メートルに達し、北前船が直接着岸できる数少ない港として重宝された。丘側は運河「高瀬通し」が通され、備中北部から高瀬舟が往来。交易の発達によって、堤防の上に蔵が建ち、問屋街の「新町」や、仲仲買人の「仲買町」に屋敷や船宿が軒を連ねるようになり、元禄年間に最盛期を迎えた。

▲藪内流の茶室が佇む『西爽亭』の庭。1780年代頃の築と伝えられる。『旧柚木家住宅(西爽亭)』(倉敷市玉島3-8-25
電話086-522-0151)※縁側からのみ見学可能
そんな玉島に、諸国を巡る北前船が物資とともに各地の文化や文人墨客も運んできた。特に商人たちの間では上方・京都の茶の湯文
化が広まり、客人をもてなすための茶室が作られるようになった。玉島の茶の湯文化は庄屋の柚木家などが広め、商人たちは接待や商談、社交の場として茶室を利用し、京都から宗匠を招いて、茶や書画、謡(うたい)、能などを嗜んだのではとされる。明治時代に入り、政府の通貨政策や鉄道が敷かれるなどの近代化によって港の勢いは失われたが、お茶文化を愛する心は今も変らない。

▲瀬戸内旅情あふれる玉島。画壇は玉島の景色と人情を愛したという。
玉島といえば円通寺の「良寛茶会」が県下四大茶会として有名である。また地元の幼稚園や学校でお茶の時間を設けるところもあり、まちづくりの観点からお茶文化を発信する活動も行われている。「初心者の方も気軽に参加できるお茶席や体験、またお茶と和菓子の店が立つ朝市もあります。お茶を通して玉島を知っていただけたら、うれしいです」と「玉島湊まちづくり推進協議会」代表の猪木直樹さん。玉島では子どもから大人までお茶に親しんでいる。

▲老舗の『いぎ呉服店』があるなど、昭和レトロな雰囲気が映画のロケ地にもなった「通町商店街」。毎月第2日曜に「備中玉島みなと朝市」を開催。お茶と和菓子の店も登場する。
お茶の魅力について、茶人である器楽堂ゆう子さんに伺った。「茶道には『直心』という言葉があります。これは、水が流れるように自然で素直な心を表します。たった一服のお茶が、心を静かに整えてくれます。茶室に座り、三口半で飲み切る短いひと時のために作法のすべてがありますが、それは直心、心の在り方を大切にするためなのです」。
玉島は茶道具専門店や和菓子店、お茶の専門店、呉服店などが多く、それは風流を愛する心が根付いている証。江戸時代から続くお茶文化に触れながら、改めて玉島の散策を愉しみたい。
『玉島のお茶文化』の体験はこちら
●『器楽堂老舗』のお茶会 (予約不要)※毎週日曜日開催
江戸末期から7代続く茶道具、花器などの店で初心者でも気軽にお茶体験ができる。玉島の歴史講和なども愉しみにしたい。
住所:倉敷市玉島中央町1-17-5
電話:086-522-2309
営業時間:9:00頃~16:00頃
料金:500円
URL http://kirakudourouho.tblog.jp/
※『オセラ2024年12月25日号』にて掲載。
※掲載の情報は、掲載開始(取材・原稿作成)時点のものです。状況の変化、情報の変更などの場合がございますので、利用前には必ずご確認ください。